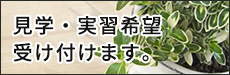久々のアップですね。
介護保険の改正による大減収。
潰れる施設も出てくるかもしれない状況の中、私たちも例外なくとっても厳しい…。
そんな話を前回書いていましたが、その対策と様々な困りごとや研修企画等個人的都合もありバタバタしていましたところ、気づいたら日記の書き込みがこんな時期になってしまいました。
久々の書き込みで、書きたいことはたくさんありますが、前回に引き続き介護保険の加算になっている看取りについての思いを・・・と思います。
終活をテーマにエンディングノートや相続税の値上げもあって自身の資産管理、はたまた葬式体験まで、死にまつわる事が一つの流れのような風が吹いているように感じてしまいます。
そして、この介護保険の流れも例外なく…。
最近、多く聞かれるのは“看取り出来ます”という施設が増えてきたよね。という声。
確かに、状態が悪くなって、親しみのある部屋や仲間がいるところから最後に離れて最期を迎えるのはとっても寂しいこと。
その当事者である本人や家族、親族の思いはとても重いものです。
今、上映中で天童荒太が7年を費やして書き上げた直木賞小説の「悼む人」
死と愛、罪と償い、様々な感情とともにとても多くを感じさせてくれる作品です。(詳しくは本か映画を見てね)
この小説を読み進めると自分は誰を大切に思い、誰に愛されたのかを考えさせられると同時に、看取るってなんなのだろうと考えてしまうのです。
そして、看取りということを考えた時「その看取りは偽善なのか自己満足なのか」と、自身の姿を振り返り考えてしまうのです。
看取りなのか?ここで死ねますなのか?
「より意味のある看取りを」と言うが、意味のある看取りってどういうものなのか?
実は、真の死について誰もしっかりと語っていないところもある。
どんな科学者も専門職としての実践者も死について考えることは、宗教哲学ははずして考えることはできない。
ホスピスをメインにした病院もキリスト教など何らかの宗教哲学が基になってクライアントを支えていく。
あの20世紀最大の物理学者であるアインシュタインも「宗教無き科学は盲目である」とさえ語っているです。
さて、私たち支援者はどうなのだろうか。
まさかその人への“想い”と言うものだけで支えようとしていないだろうか。
看取りを科学的な形式知の型にはめて考えていないだろうか。
天童荒太氏は、この作品を作るために様々な死の場所を巡礼し、死の悲しみと無念さを自身の体の中に入れて考える供養をして歩いたと言います。
私たち支援者は人の最期に携わる部分に多く接する位置にいます。
死を考えると、必ず生について考えざる得なくなる。
いかに死ぬかは、いかに生きるかに繋がり、いかに生きるかは、いかに死を迎えるかに繋がっていく。
生死一体の考えを巡らしたとき、私たち支援者の立場は、今生きる目の前のその人をどう支えるのかに精一杯力を注ぐ事であって、死を特化して考えるものではないのではないかと思うのです。
看取りは、日々の繰り返される暮らしの中にこそある。
その繰り返される日々の暮らしの中で、一瞬一瞬の繰り返される心の交流と想いの積み重ねが看取りの想いとなっていくのだと思うのです。
となれば、看取りだけできるというのは何となく違うであろうし、最期を迎えるときに積み重ねた心の想いの交流がそこにないと看取りではなくなってしまうのではないかと・・・。
やはり、看取り加算は在宅で支援するもの(チーム)にも、いや、もの(チーム)にこそ必要なのではないだろうか・・・。
悼む人を通じて感じたことでした。
ちょっと重たい話でしたね・・・。